和菓子作りに欠かせない素材のひとつが、寒天です。
羊羹や水ようかん、錦玉羹、あんみつなど、さまざまな和菓子に使われます。
ここでは、
寒天の特徴・種類・基本の使い方と、
失敗しにくくするためのポイントをまとめました。
皆さまの和菓子作りの参考になれば幸いです。
寒天とは?
寒天は、
テングサやオゴノリなどの海藻から作られる、
天然の凝固剤です。
鍋で煮溶かし、
冷ますことで固まります。
特徴
- 常温で固まる
(ゼラチンと異なり、冷蔵庫に入れなくても固まります。
固まる温度はおおよそ30℃以下) - やや固めの食感
歯ごたえがあり、ゼラチンよりもしっかりした食感です。 - 砂糖を加えると透明感が出る
砂糖を加えない場合は、白く濁った仕上がりになります。
種類
寒天には主に、次の3種類があります。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 棒寒天(角寒天) | 棒状。原材料はテングサやオゴノリ。水で戻してから煮溶かします |
| 糸寒天 | 糸状。原材料は主にテングサ。水で戻してから煮溶かします |
| 粉寒天 | 粉末状。そのまま使えるため扱いやすく、水に振り入れて煮溶かします |
家庭でよく使われるのは粉寒天ですが、
和菓子では 棒寒天や糸寒天 もよく使われます。
※ 私自身は、主に 糸寒天 を使っています。
寒天の使い方
寒天の基本的な使い方
◎ 棒寒天・糸寒天の場合
① 寒天を水で戻す
- 寒天を計量する
- ボウルに入る大きさにカットする
- ほぐして、多めの水に 6時間以上 浸す
棒寒天も、同じ方法で戻します。

② 鍋で煮溶かす
- 戻した寒天を軽く洗う
- 分量の水とともに鍋に入れる
- 中〜強火で 2〜4分 加熱し、完全に溶かす
(※分量によって時間は前後します)
棒寒天の場合は、
細かくちぎってから鍋に入れると溶けやすくなります。

③ 漉す
寒天液をザルで漉し、
溶け残りを取り除きます。
この寒天液に
砂糖やあんを加えて煮詰めると 羊羹や水ようかん に、
そのまま型に流して冷やすと あんみつ用寒天 になります。

◎ 粉寒天の場合
① 煮溶かす
- 分量の水に粉寒天を振り入れる
- 中〜強火で 2〜4分 加熱し、完全に溶かす
火を止めたら、寒天液の出来上がりです。
漉す必要はありません。

寒天を使うときの大切なポイント
ポイント①:火加減は中火〜強火
寒天は火にかけたら、
中火〜強火を保ちましょう。
寒天をしっかりと溶かすことが出来ます
寒天が溶ける温度は 約80℃前後。
火が弱いと、完全に溶けず、固まりにくくなります。

ポイント②:煮溶かす際、アクは取らない
寒天を煮溶かしていると、
アクのようなものが浮いてくることがあります。
つい取りたくなりますが、
これは寒天の成分です。
取り除いてしまうと、
寒天が固まらなくなる原因になります。

ポイント③:砂糖は寒天が溶けてから加える
砂糖を加えるのは、
寒天が完全に溶けてからにしてください。
寒天が溶ける前に砂糖を入れると、
それ以上寒天が溶けなくなってしまいます。
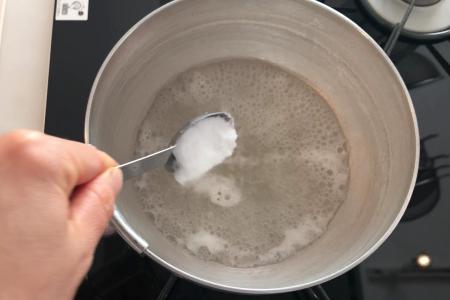
ポイント④:酸を加える場合は火を止めてから
寒天は 酸性に弱い 性質があります。
- レモン汁
- 柑橘の果汁
などを加える場合は、
必ず 火を止めてから。
寒天が固まり始める直前、
45〜50℃前後で加えるのが目安です。

まとめ
- 寒天は常温で固まる
- 寒天の種類によって使い方が異なる
- 完全に煮溶かすことが最大のポイント
- 基本が分かれば、応用はとても簡単
寒天の特徴を理解すると、
羊羹・水ようかん・錦玉羹などの和菓子作りが、
ぐっと楽しくなります。
基本を押さえたら、
ぜひいろいろな寒天菓子に挑戦してみてくださいね。








